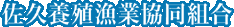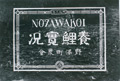全国ブランドとして名高い「佐久鯉」の起こりは、古く江戸時代の1592年(文禄年間)。当時、佐久の中込地方において野性ゴイの飼育(ボラゴイ)を試みたことが村話として伝えられています。
やがてその技法が受け継がれ、歳月をかけて佐久の気候、風土と千曲川の清流と伏流水が、身の締まった美味しい鯉を育て上げて来ました。そして昭和初期には全国一の生産量を誇り、鯉の博覧会や品評会でも、その優れた品質で日本一の称号を得ました。当時、宮内省や陸軍のご用達の栄を賜ったことは、その名声を今に伝えるものです。
他の産地の鯉は通常2年程で出荷されますが、佐久鯉は冷たい流水で飼育されるためその成長が遅いのが特長です。しかしそれだけに臭みもなく、身が引き締まって脂肪が適度にのった美味しい肉質となります。また、最近では米の無農薬栽培をすすめる農家によって、水田養鯉の取り組みも復活しています。
佐久鯉

日本産の他地域の鯉に比べ、佐久鯉は体高が高く成長も良い。ドイツ鯉や在来種との交配により生まれた。
-
在来種の鯉

一般に佐久鯉と称される魚に比べ体高が低い。
ドイツ鯉

背肉が盛り上がって体高が高く、成長も良く優れていたが、ウロコが少ないためあまり好まれなかった。
| 西暦 | 年号 | できごと |
|---|---|---|
| 紀元前100年頃 | このころ中国に養鯉始まる。 | |
| 1592-95年 | 文禄年間 | このころ佐久の中込地方において、野生ゴイの養成(ボラゴイ)を試みる。 |
| 1630年 | 寛永7年 | 五郎兵衛新田用水路完成(浅科村・五郎兵衛米) |
| 1781-88年 | 天明元年 |
|
| 1804年 | 文化文政期 |
|
| 1842年 | 天保13年 | 佐久跡部村茂原猪六、慶応年間までの「養鯉日記」を記す。 |
| 1870年 | 明治3年 |
|
| 1875年 | 明治8年 |
|
| 1884年 | 明治17年 |
|
| 1895年 | 明治28年 |
|
| 1902年 | 明治35年 |
|
| 1906年 | 明治39年 |
|
| 1923年 | 大正12年 |
|
| 1924年 | 大正13年 |
|
| 1925年 | 大正14年 | 全国副業展覧会が東京上野で開かれ、佐久鯉一等入選。「佐久鯉」使われ始める。佐久鯉加工工場できる。 |
| 1926年 | 大正15年 昭和元年 | 「南佐久水産会」設立。 この年、東京出荷19トン。 |
| 1930年 | 昭和5年 |
|
| 1931年 | 昭和6年 | 国鉄に「ナ1形活魚車」登場、米原駅常備。昭和8年東京出荷300トン |
| 1954年 | 昭和29年 | 佐久養殖漁業協同組合。設立 |
| 1955年 | 昭和30年 |
|
| 1957年 | 昭和32年 |
|
| 1962年 | 昭和37年 |
|
| 1963年 | 昭和38年 |
|
| 1964年 | 昭和38年 |
|
| 1966年 | 昭和41年 |
|
| 1967年 | 昭和42年 | 橋幸夫さん「佐久の鯉太郎」レコード発売。 |
| 1969年 | 昭和44年 | 「佐久鯉太鼓」発足し、地域の活性化をはかる。(現在も活動中) |
| 1973年 | 昭和48年 |
|
| 1979年 | 昭和54年 |
|
| 1983年 | 昭和57年 | NHK「明るい農村」で佐久鯉が放送される。 |
| 2003年 | 平成15年 | 茨城県霞ヶ浦にてコイヘルペスウイルス病(KHV病)感染、長野県内でも感染が確認。 |
| 2008年 | 平成20年 | 9月12日。地域団体登録商標『佐久鯉』登録される。 |